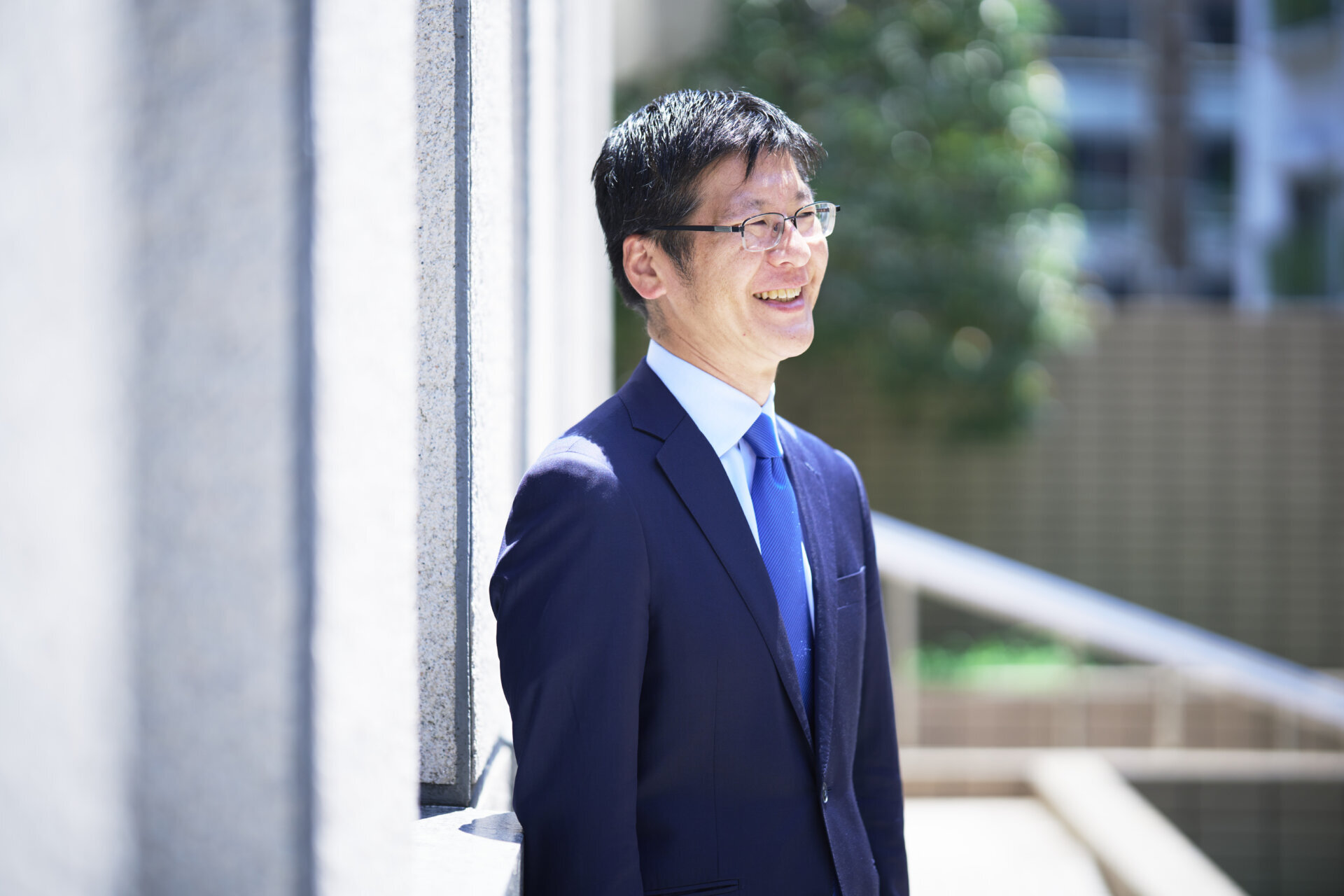E.JOURNAL
インタビュー
『E.ジャーナル』はメンバーが「いま気になる人」に“学び”をテーマに取材していく、EXD.Groupオリジナルコンテンツです。第7回目のゲストは、日本イベント産業振興協会(JACE) サステナビリティ委員会委員長の越川延明さんです。
イベント業界におけるサステナビリティの必然性
日常生活の中で「サステナビリティ(Sustainability)」という言葉を耳にする機会が増えました。サステナビリティとは「持続可能性」を意味し、将来の世代が必要とする資源や環境を損なうことなく、現在の社会・経済活動を継続できる状態を指します。環境保護、社会的責任、健全な経営といった視点を総合的に捉え、長期的に価値を生み出す仕組みを築くことがその目的です。
こうした考え方は、さまざまな産業にも広がっており、イベント業界も例外ではありません。イベントは人々の交流を生み、経済や文化を活性化する一方で、大量の資源消費や廃棄物、CO₂排出、さらには長時間労働といった課題も抱えています。だからこそ、企画から運営・撤収・評価まで、あらゆる段階でサステナビリティを意識することが不可欠です。
こうした課題を解決し、業界全体で持続可能な運営を推進することを目指して2024年に策定されたのが『イベント・MICE関係者のための 使いやすいサステナビリティガイドブック』。今回はその策定に中心メンバーとして携わった、JACEのサステナビリティ委員会委員長を務める、株式会社セレスポの越川延明さんにガイドブック誕生の背景や今後の展望について伺いました。
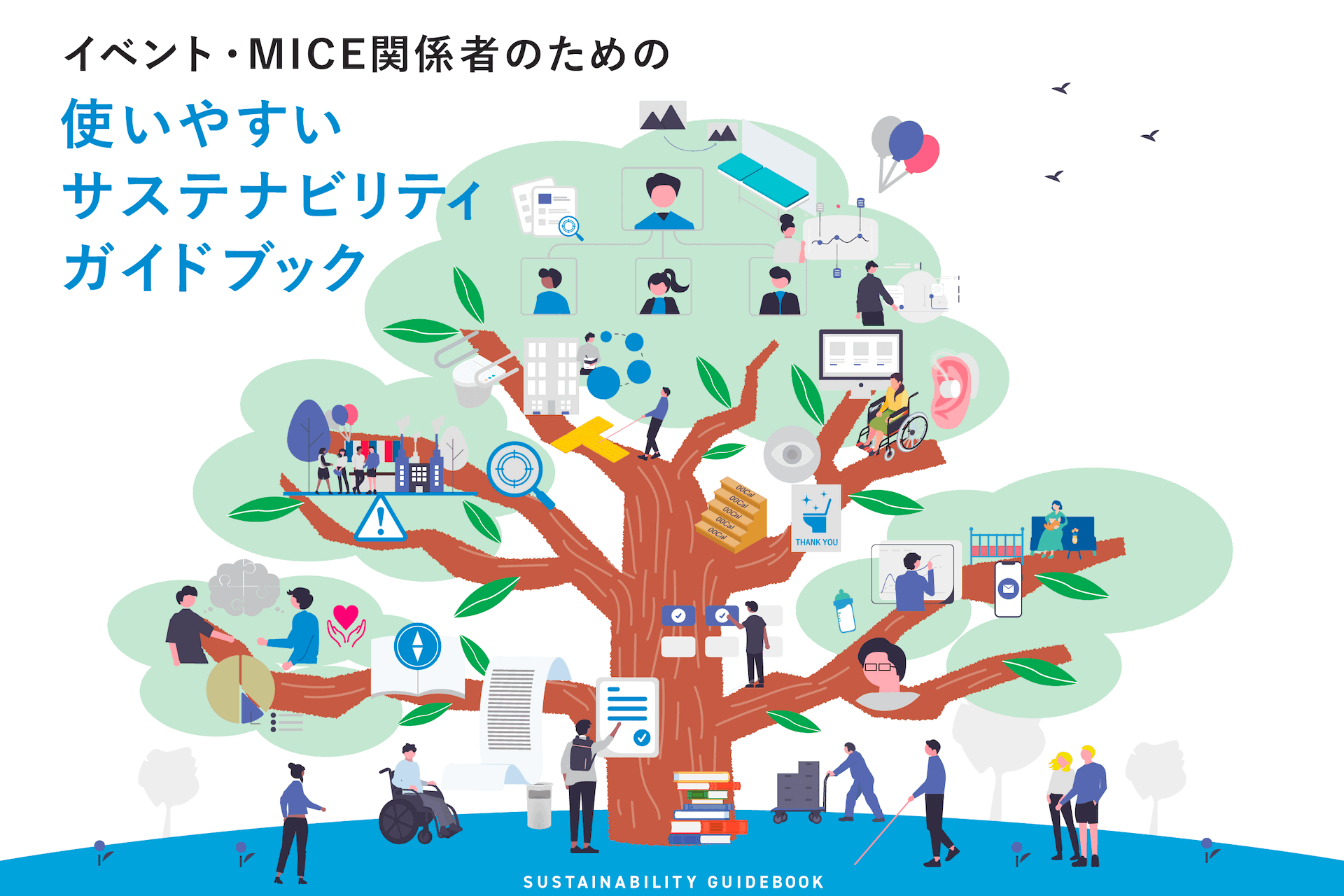
越川さんの歩み ― サステナビリティとの出会い
「大学卒業後は漠然と教師になろうと思っていたのですが、最終面接の直前くらいに教員だった母から『あんた、自分が思うままに行動するから先生に向いてないよ』と言われて。『今頃、言うなよ!』と思ったのですが、確かにその通りだなと(笑)。それでもともと好きだったイベントの世界に飛び込みました」。
そう振り返る越川さんは、2001年にイベント制作会社のセレスポに入社。地域密着型のイベントを中心に、スポーツイベントやセレモニーなど幅広い案件を経験してきました。
現在は人事・総務・広報を担当していますが、入社当初は現場での施工などを担当。強い雨の中での設営撤去など厳しい労働環境に直面することもありましたが「参加者や主催者が喜んでくれたり、楽しんでいる姿を見ると、嬉しくて疲れがすべて吹き飛びました」と越川さん。その後、営業職や社長のアシスタントなどを経て、「サステナビリティ」というテーマに出会ったのは2010年頃のことでした。

きっかけはロンドン五輪。イギリスの国内規格を国際規格へと転換する流れの中で、越川さんはJACEに出向し、規格の策定に携わることになったのです。「当時は“サステナビリティ”という言葉自体、ほとんど浸透していませんでした。しかし、気候変動や教育格差といった課題が溢れる中で、社会のアンバランスさを感じていた自分にとって自然と関心を持てるテーマでした」。
そして、このテーマに取り組むさまざまな経営者や有志と夜な夜な集まって勉強会を開催したと話します。「ニュースで見るような方たちとご飯を食べながら『今日はこんな情報を見つけた』『海外ではこういう事例があるみたい』と情報共有をしたり、知恵を出し合ったり。濃密な時間を過ごせました」。
その成果として2012年には『ISO20121:イベントの持続可能性に関するマネジメントシステム』を策定。「発表すると反響があって、新たなトレンドが生まれる源流に携わることができました」と振り返りました。
“はじめの一歩”を踏み出すためのガイドブック
サステナビリティに関する知見を積み重ねた越川さんが『イベント・MICE関係者のための 使いやすいサステナビリティガイドブック』の策定に関わる契機となったのが、大阪・関西万博の開催でした。巨大イベントを前に業界横断で基準を整える必要性が高まったのです。「JACEをはじめ、さまざまな業界団体で基準を設けようという動きがありました。それならば共通の指針を一つにまとめ、万博のレガシーとして残そうと策定が始まりました」。
ガイドブックの策定にあたって重視したことの一つが「教科書のようにしない」こと。「理念としてただ“良いこと”だけ書いてあるのではなく、会社の規模や業態に応じて取り組みやすい具体例を提示して、実践に活かせるものにしたいと思っていました」と越川さん。そこで採用されたのが一定の基準値を設けるのではなく、それぞれの組織が可能なアクションを選べる“ビュッフェスタイル”の見せ方です。
「大手はここまで挑戦してほしい、一方で初めて取り組む企業は無理なく小さなことからと、まずは“はじめの一歩”を肯定したいと思っています。基準値だけだと『ここまでやれば、もうOK!』という感覚になってしまいますが、サステナビリティではその先も取り組み続けることが大切です」。

多様性が広げる、新しい視点と可能性
ガイドブックでは「環境」「人権」「社会効果」の3つを、サスティナブルなイベントを考える際の柱としています。その中から、EXDグループとして気になることを聞いてみました。
まずは“アルバイト”について。私たちもイベントの規模によってアルバイトを数多く雇用することがあり、その対応に配慮しています。「この文脈でいう人権とは、当人が働きやすいように働き、自己実現できる環境のことです。例えば、本当は社員になりたいものの事情によってアルバイトをしている人がいれば、会社の成長に合わせて無理のない範囲で雇用したり、現場ではなく地道に働きたいという人がいればバックオフィスのサポートに充てたり。アルバイトに限らず一人ひとりの状況を会社が理解して対応することが重要です」と越川さん。さらにハラスメントなどの対応として、独立した相談窓口の設置などについてもアドバイスをくれました。

女性社員の割合が多いのもEXDグループの特徴の一つ。セレスポでも近年、女性社員が増加しており、出産や育児などをサポートする福利厚生の制度も手厚くなるように見直されているそうです。「元々、イベント施工を中心にしていた会社なので男性が多かったのですが、女性にできないわけではないですし、そのほかの仕事も多岐にわたります。そういえば、この間も大雨の中のイベントで男性の新入社員がぐったりしている横を、女性の新入社員が『イベントやってる感ありますね!』と楽しそうに走り回っていましたね(笑)」。
さらに、女性や外国人など条件やバックボーンが異なる人が組織にいることで、働き方などの見方も広がった例を越川さんは紹介してくれました。「外国人の社員が増えてきた制作会社の話です。日本語だった会社マニュアルを動画に変えてみたら、日本人の社員にもわかりやすいと好評だったようです。背景や前提条件が異なる人がいると、従来の仕組みがより良い形にアップデートされたり、新しい発見や可能性が生まれやすくなります」。
イベントを“社会実験”の場に
今後、ますますサステナビリティの意識が高まっていくことが予想されるイベント業界。その展望について尋ねると「“エコ”という言葉が当たり前になったように、サステナビリティも自然と意識の中に刷り込まれている“サステナビリティ ネイティブ”の世代が登場すると思います。そういった人たちがイベントを“社会実験”の場として使ってもらえれば」と言い、さらに続けました。「イベントは一度限りの場だからこそ、新しい挑戦ができます。例えば大阪・関西万博が思い切ってフルキャッシュレスにしたように、成功も失敗も含めてフィードバックできる。イベントはそうして社会に影響を広めていく実験の場にすることができます」。

インタビューの最後に、ご自身の今後についても伺いました。「アスリートでもアーティストでも、世の中には何かを表現したい、何かを変えたいと思っている人がいっぱいいます。サステナビリティに限らず、そのテーマに対して熱い想いを持っている人たちが、少しでも活躍できる世の中にしていく。それでより社会が豊かになっていく力になれれば嬉しいですね」。
近頃、“Empowerment”という言葉が気に入っていると越川さん。日本語では「勇気づける」「力を与える」と訳されるこの言葉に自身の姿勢を重ねながら、誰かの想いや挑戦を後押しする存在として、イベント業界の未来を見据えています。

■日本イベント産業振興協会(JACE) Webサイト
https://www.jace.or.jp/
取材・原稿:遠藤啓太 撮影:伊藤有宏